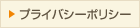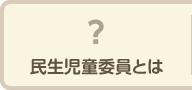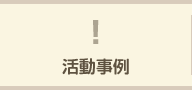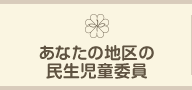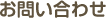小春日和に恵まれ、桜ケ丘ハイツ地区社協主催の「喜寿のつどい」が開催されました。
桜ケ丘民児協を始め関係団体と協力参加し、45名のお客様をお迎えしました。
晴れの日にふさわしく、東可児中学生の琴演奏から始まり、続いてシャンパンでの乾杯・
お食事・ハーモニカ演奏(上田さん他3名)と、和やかな雰囲気の中で祝賀の会が進んで
いきました。ハーモニカ演奏では懐かしい曲に口ずさまれる方、にこやかに聞き入っていらっしゃる方、お一人お一人の歩まれてきた人生がそこにあり、今日もその1ページになったことと思います。
また中学生が抹茶を点ててお客様まで運び、おもてなしにも参加しました。
お帰りの際の皆様の笑顔からご満足していただけた様子が伺え、スタッフ一同元気をいただきました。


今月の子育てサロン「さくらっ子」は、参加者がいつもより少ないように感じられました。
同時に開かれている0~1歳児を対象とした「すくすく教室」が今回たまたまお休みだったからだと思われます。が、その分ゆったりと落ち着いて会話・対話ができたのではないでしょうか。
恒例となっている子育てサロンですが、最近はいろんな意味で広がりをみせているようです。
例えば、母親だけでなく祖父母の方がお孫さんの手を引いて参加されたり、遠方に住まわれている知り合いの方に呼び掛けて一緒に参加されたり様々です。今回は小牧在住の妹さんに連絡して参加された地元の方がいらっしゃいました。
落ち着かないファミレスなどで時々会って話をするより、子育てサロンを利用してゆっくり話した方が楽しい…とのことです。
年齢や居住地の幅を超えて文字通り「地域のサロン」として広がっていってくれたらどんなにいいことでしょう。


毎年この季節に行われている視察研修。今回は午前中に岐阜県広域防災センター、午後から各務原浄化センターを訪ねました。
防災センターでは、火災で煙が充満した状況での避難を体験したり、備蓄倉庫を見学したり、消火器の操作訓練を行ったりしました。また、地震体験装置で震度7の揺れ、内陸型地震と海溝型地震の揺れの相違なども体験できました。
浄化センターでは、下水道処理の概要をビデオで見た後、広大な水処理施設に移動して説明を受けました。独特の臭いのする汚れた水がきれいな水へと変化していく過程がよくわかり、木曽川への放流まで見学することができました。
両施設とも係の方がとても丁寧に対応・説明して下さり、好天にも恵まれて充実した一日になりました。
確実に来るといわれている南海トラフを震源域とする大地震への備え、家庭での生活用水のあり方、などまだまだやること・考えることは盛り沢山です。


8月16日 (火) 蝉しぐれのなか、参加児童は低学年を中心に35名ほど。指導員の方々と、地域ボランティアで民生児童委員も加わり、かき氷、綿菓子を作りました。
例年に比べ 若干児童数も少なく、ボランティアの方も気楽に会話も弾み、注文に応じてかき氷は三色オリジナルにしたり、綿菓子も大や小にふんわりと仕上げ、大喜びで行列が出来るほど。車座になって頬張る姿は微笑ましく、バルーンアートを楽しんだり、室外のヨーヨー風船釣りに興じたり、賑やかな夏祭りでした。


恒例となった桜ヶ丘民児協主催の「救命講習会」が8月3日開催されました。
今年の受講者は16名、指導にあたるのは加茂消防組合南署の消防士、救命士のお2人です。
概要説明の後、胸骨圧迫 (心臓マッサージ) の実技に移りました。
1分間に100回のリズムで圧迫を繰り返すのですが、1分間持続は思ったよりきつい。
続いて人工呼吸の実技。以前と違ってこの人工呼吸は場合によっては省略可とのこと。
あくまでもメインは胸骨圧迫で、救命法も時とともに変化していることを実感します。
そして、AEDの使用法の説明の後、実際に倒れている人を発見したとの想定のもと、
胸骨圧迫からAED使用に至る一連の手順を各自が一通り行いました。
消防訓練や避難訓練同様、一度やっただけでは覚えられるものではありません。
毎年繰り返すことで少しずつ身についていくものだ、ということを改めて認識した講習会でした。