あなたの地区の民生委員・児童委員
下記のマップからあなたの地区をクリックすると、地区ごとの委員紹介・活動紹介を閲覧できます。
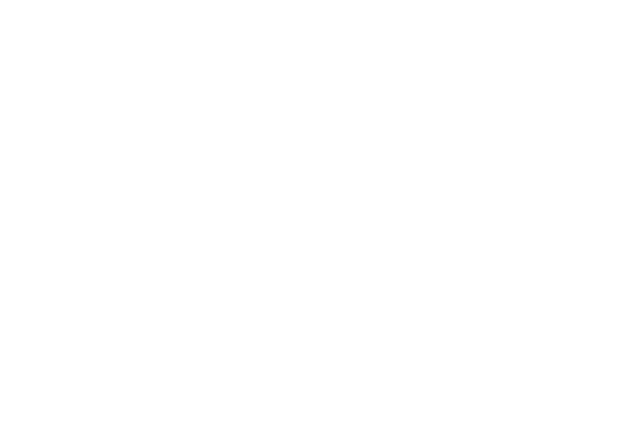
下記のマップからあなたの地区をクリックすると、地区ごとの委員紹介・活動紹介を閲覧できます。
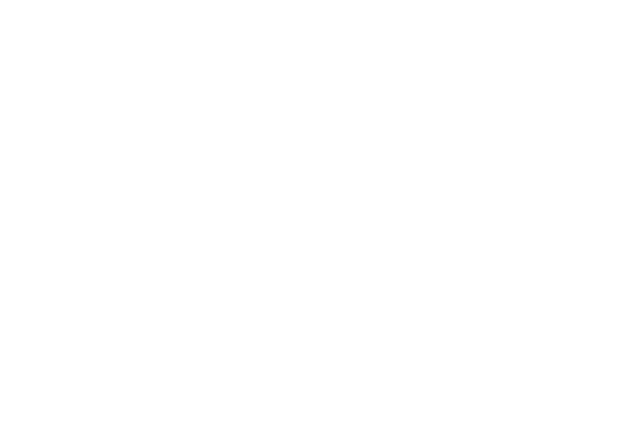
南帷子民児協は、6月26日(木)新岐阜県庁舎の施設見学を行いました。新県庁舎は5代目の建築物であり、4代目の庁舎施工から56年目が経過し、耐震性や狭あい化などの課題があったため、県の災害対策の中枢拠点そして「清流の国ぎふ」の魅力を発信する庁舎となるよう再整備されたとのことでした。
新庁舎の基本方針は、
〇 県民が集い親しまれ、地域の魅力を発信する県庁舎
〇 安全で安心な県民の暮らしを守る県庁舎
〇 環境やライフサイクルコストに配慮した県庁舎
ということであり、県職員のご案内を頂き多くの施設を見学しました。
1階行政棟では、総合案内カウンターに飛騨の伝統技法「千鳥格子」の組み込みや「美濃和紙」や「県産ヒノキ材」「県産タイル」を使用した各フロア、さらには「ギャラリーGIFU」では県内地場産品の展示など見どころがいっぱいでした。
20階行政棟では、岐阜の山々や街並みを一望できる展望ロビーや第4代県庁舎から移設された「モザイク壁画」など見学を行いました。
次に議会棟に移動し、6階議場傍聴席より5階の議場(休会中)の見学や議会棟北側にある「ぎふ結のもり」では、災害時におけるきめ細かい防災機能などの説明を受けて感動し、有意義な研修を終えることができました。
朝から気温が高く蒸し暑い中、参加者の出足が遅かったですが、4組の大人と子どもさんの参加がありました。始めは、いつもの通り準備して置いた遊具で、子どもたちは元気よく遊んでいました。途中から「音あそび」で、音の出る楽器やおもちゃで自由に道具を動かして楽しんでいました。今月は、食育月間で19日は「食育の日」でもあり、講師を呼んで、おみそ汁の子ども用(0.4%)と大人用(0.8%)の飲み比べをしました。小さなお子さんも喜んで飲んでいました。又お話で、特に朝ごはんは、1日の生活リズムを整えるのに大切であることも学びました。
当サロンでは、お母さん同士がお茶を飲みながら、親交を深める和やかな時間も作っています。今回も親子共々、楽しい時間を過ごすことができました。
6月12日(木)、南帷子小学校の奥村校長先生を帷子地区センターにお招きし、南帷子民児協との話し合いを持ちました。
奥村校長先生からは学校での子供の学習状況や子供同士の関わり方、生活態度や学校内での過ごし方などの現況をお伺いしました。
最後に、校長先生から「学校との敷居を低くしますから是非学校内での定例会を実施してください」とのご意見を頂き、前向きに実施する方向で懇談会を終わりました。
「令和7年度 帷子センターまつり」が今年も帷子地区センター敷地内において開催され、地域の多くの皆様(約3000名)が来場し盛大に行われました。
帷子地区民生委員児童委員協議会は帷子地域福祉の増進を図るため、この「帷子センターまつり」に昨年同様、両協議会が相互協力のもとに参加し、民生委員児童委員の日常における活動内容を広く地域の皆様に周知・理解して頂くことを目的として次の3事業を実施しました。
〇 民生委員児童委員の活動紹介パネル展示及び各種資料配布
〇 白米・規格外人参その他の格安販売
〇 コーヒーの無料提供
などを中学生ボランティアの皆さん(25名)と一緒になって実施しました。
パネル展示では、高齢者や子ずれの若い夫婦らが来場し、委員からの説明を受け「民生委員児童委員の皆さんは地域のつなぎ役であり、何かあれば気軽に相談させてもらいます」と笑顔でその場を離れる方もみかけました。
また、子育てサロンコーナーのシャボン玉体験では、多くの子供たちが大きなシャボン玉作りに大喜びでした。
格安販売には販売開始前から行列ができる程の盛況で、全て完売しました。
コーヒーの無料提供コーナーでは、約520杯のコーヒーを提供し、皆さんから笑顔で「今年もありがとう、美味しいです」と感謝のことばを頂きました。
最後に、参加した委員全員の集合写真を撮り、実行委員長からの慰労挨拶を受け「帷子センターまつり」を無事に終わりました。
朝から晴天で、気温も少し高いところ4組の大人と子どもたちが参加してくれました。本日のテーマは、「カラーボールで色あそび」をしました。初めは、サロンにある遊具を出して遊びました。歩けるようになった子どもたちが、プールにボールを入れたり、ボールを持って投げたり、座り込んで遊んでいました。お気に入りのボールを抱えて離さない子や滑り台の上まで両手にボールを持って上がり、バスケットネットの籠に入れたりしている子もいました。又、床からバスケットネットに入れようと、何度もチャレンジしている頼もしい男の子や大玉を上手にころがして、嬉しそうな女の子もいました。子どもたちが慣れたところで、母親同士のおしゃべりコーヒータイムも好評でした。親子共々、賑やかに楽しい時間を過ごしてもらいました。
次回6月19日(木)子育てサロンの主なテーマは、「おとあそび・食育教室」を予定しています。スタッフ一同、多数のご参加をお待ちしております。