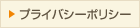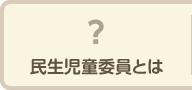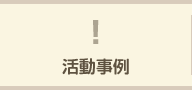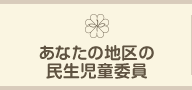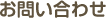私達桜ヶ丘民児協は、今年も75歳以上のお一人暮らしの方々をお招きして年に一度の『ハイツふれあい会』を催しました。9人のプロジェクトメンバーが早くからアイデアを持ち寄り、何度も打ち合わせを重ねて本番をむかえました。
今年はハイツ在住の声楽家の鵜飼慶子先生にミニコンサートをお願いしてお客様に楽しんでいただくことを計画しました。プッチーニの歌曲をはじめ日本の名曲合わせて6曲を歌っていただき、プロのオペラを堪能させていただきました。お客様方も先生の美声にうっとりと聴きほれていらっしゃいました。
コンサート終了後はお汁粉とお茶でくつろいでいただき、第2部は福祉サービスのお知らせ、手指を使って脳トレの小箱作り、見守り対象の方が作られた短歌の朗読と皆様に楽しんでいただこうと役員一同精一杯がんばりました。
『今日は本当に楽しかった』と皆様からねぎらいの言葉と共に言ってくださり、充実感を味わうことができました。


回を重ねて今では、桜ケ丘児童センターの新春恒例行事となり、約150名(幼児と小学生60名と父兄方ならびに支援者)もの参加がありました。
各種支援団体の担当も決まっており、チーム内の蓄積されたノウハウで作業は順調に進みました。民生委員の担当は「お米蒸し」から「もちつくり」までの一連の作業ですが、男性陣が「もちつき」に当たりました。また青少年育成推進委員は、このイベントに欠かせない「豚汁つくり」。助っ人には桜クラブの皆さんも参加してくれました。
今年は全国的な「ノロウイルス集団感染」の影響で、「手洗い励行」と「マスク着用」は勿論のこと、出されるもちは「きな粉もち」と「いそべもち」のふた種類になりました。幼児童たちは、子供用の小ぶりの杵でもちつきを体験しました。
参加時に4色の組分けされたチームの全員が先生の「いただきます」の挨拶の後、出来あがった「もち」と「豚汁」に楽しいトークも加わり美味しく頂きました。食後にはチームごと円陣を作り、児童センターならではの「ゲーム風音楽体操」で、世代を超える触れ合いを通し、絆を確かめ合いました。
ハイツでは近年街づくりの一環として、種々のふれあい活動が進められており、このようなイベントが伝統文化と言える催しのない団地の歴史文化の一つに育ってくれることを願っています。

「毎年、桜ヶ丘ハイツ内の喜寿の方を公民館にご招待しています」。田原・地区社会福祉協議会長が約40名の方に挨拶をして集いが始まりました。
アトラクションはフラダンス(アロハ・ケイ・フラスタジオの皆さん)。ハワイの歌と踊りでハワイムードいっぱいです。食事はビール・ワインで乾杯し、会場にBGMが流れる中で心づくしの折詰に箸がすすみました。大好評の宮野陽介さんによるショーはトランプ、リング、ロープなどを使っての鮮やかなマジックを堪能しました。
曲当てクイズやビンゴゲームは参加者もボランティアスタッフもみんなで歌って楽しむ手作りの趣向です。「ビンゴ」と手を挙げた車いすで参加の方は、長年の車いす生活を奥さんが前向きに全力で介護をされています。今日の参加に不安もありましたが、担当民生委員の声掛けや自治会副会長のサポート、もちろん奥さんの同伴で楽しんでいただきました。景品で選んだ花束を奥さんに渡されました。言葉がなくてもそれは「いつもありがとう」と感謝の気持ちのようで、ホッとしました。
喜寿の方全員一緒に記念撮影をしてお開き。温かい空気のつつまれた、手作り感いっぱいの喜寿の集いが無事終了しました。


建部地区民生児童委員8名の方をお迎えして交流会を行いました。
可児市民児連の奥村会長から可児市民児連全体の共通した取り組みを説明、建部地区民児協と桜ケ丘民児協の会長から各民児協の活動状況の説明を受けて意見交換を行いました。
双方の民児協とも地域の各種団体と協力しながら、高齢者・児童の見守り活動を行っていることで参考になることを学びあいました。
建部地区民児協の活動で興味をひかれたのは、認知症徘徊者の捜索訓練をしていることです。そのため、しっかりした組織の下で、行方不明者の特徴を配布して実践さながらの捜索を行い、成果を上げている様子に感心しました。
個人情報の保護が民生児童委員活動に大きなネックになっていることが共通の話題となりました。東近江市でも「活動に必要な情報が市から得られなく、日常の活動に困ることが多い……」という話があり、〝個人情報保護という壁〟を互いに実感しました。民生児童委員の日常活動が支障なくできるよう、個人情報の取り扱いに前向きな体制ができることを期待したいものです。
桜ケ丘小学校、東可児中学校と桜ケ丘民児協の委員間で児童・生徒について情報交流を行う目的で開かれました。学校側からは校長、教頭、生徒指導主事の先生が、民児協側は島田会長はじめ16名の委員が出席しました。東可児中学校区が受け持ち区域にある東明民児協の山口会長と担当委員にも出席していただきました。
昨年度のまとめの会で民児協側から「学校での児童・生徒の様子について参観したい」というリクエストがありました。学校側のご配慮で児童の普段の様子を見られるように、掃除参観と授業参観をさせていただきました。真剣に授業に向かう子供たちの姿は、普段見ることがないだけに新鮮な感動を受けました。
生徒指導主事の先生から「小学校の現状」「中学校の現状」について説明をいただきました。「登下校時などの『あいさつ』にこだわって指導している」といわれた先生の話に地域が児童・生徒に接するときのヒントがあるように感じました。その後、意見交換を行いました。学校でしかわからないこと、家庭でしかわからないことなどを話し合い、有意義な意見交換が出来ました。