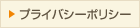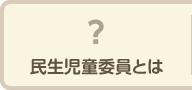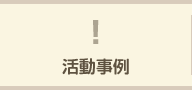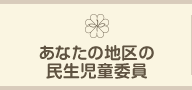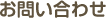可児市民生委員児童委員、主任児童委員の退任式が福祉センターで開催され、11月30日付けで退任された92人が参加しました(退任者は104名)。
冨田成輝市長から、厚生労働大臣感謝状、県知事感謝状などが伝達され、「在任期間はそれぞれですが、長い間活動していただきありがとうございました。皆様の普段の見守り活動や相談支援のおかげで住民が安心して暮らすことができます。今後もできる範囲での地域の見守りの継続、後任委員の支援をお願いします。」とご挨拶をいただきました。
退任委員を代表して渡邉孝夫さん(下切)が、「最初は不安がありましたが、見守り活動の中でかけていただける感謝の言葉が心の支えとなり、コロナ禍で制約がある中でも活動を続けてこられました。民生委員児童委員活動が円滑に行えたことは、市長をはじめ、福祉事務所、社会福祉協議会、自治連合会、そのほか福祉事業に携わる方々の温かいご指導、ご支援の賜物と思っています。心から御礼申しあげます。」と挨拶をされました。
その後、記念撮影を行いました。


可児市民生委員児童委員、主任児童委員182人が12月1日付けで就任しました。新任は104人、再任は78人で任期は3年です。
冨田成輝市長から、厚生労働大臣からの委嘱状と県知事の辞令書を受領し、委員を代表して尾関眞澄さん(川合)が、「地域住民と信頼関係を築きながらニーズや困り事、問題を早期にキャッチし、市役所や関係機関などと連携を密にし、地域住民に寄り添う支援を心がけ、安心して暮らしていただけるように一生懸命活動をしていきたい。また、委員同士、お互いに助け合って地域で貢献できるよう活動させていただきたいと思います。」と決意を述べました。
その後、新任委員を対象とする説明会が行われました。

3年ぶりに再会された姫治地区センターふれあい祭りに参加しました。
今までは「ぜんざい」を無料配布していたのですが、コロナ禍なので健康クイズを実施しました。
クイズは、大人用と子ども用を用意し行ない、参加者にとても好評でした。


7月22日、滋賀県彦根市民生委員児童委員協議会連合会広報部会の委員5人が、「ホームページの先進地視察」として可児市を訪れ、広報活動委員会、情報部会の代表らと交流会を行いました。
両会長の挨拶やお互いの活動紹介の後、ホームページへの投稿方法や運営等について、活発な意見交換が行われました。